- 育休明けに復帰したけど、時短勤務が周りに迷惑をかけている気がする
- 「すみません」と言いながら毎日早く帰るのがつらい
- 肩身が狭くて働きにくい。 このまま仕事を続けられるのか不安
残った仕事を他のスタッフにお願いして早く帰ると「迷惑ではないか」と不安になる一方で、「しょうがないじゃん」とも思いますよね。
「迷惑ではないか」と気にしていると、心にも体にも負担がかかり、「仕事に行くのがイヤだ」とも思ってしまうのではないでしょうか。
しかし、時短勤務でも働き方次第では、「あなたがいないと困る」と思ってもらえるようになりますよ。
とはいえ、あなたが「時短なんだからしょうがない」と思っていると、上司や同僚から理解されずに関係性が悪化してしまいかねません。
この記事では、「迷惑にならない仕事の工夫」や「効果的な声のかけ方」を紹介するので、最後まで読んでストレスから解放されましょう。
看護師の時短勤務は迷惑なの?
働き方次第では迷惑になりません。
勤務時間が短いことよりも、限られた時間内であなたが、「どう動くか」「どう周囲と関わるか」によって、上司や同僚から信頼されるかどうかが決まるからです。
| 信頼されやすい行動 | 信頼されにくい行動 |
|---|---|
| 患者の緊急度・優先度の高い業務から取りかかる | 今やらなくてもいい雑務から取りかかる |
| 自分の担当患者以外のナースコールも可能な範囲で対応する | 自分の担当患者のナースコールしかでない |
| 周囲が忙しいときは、時間内でできる業務をサポートする | 周囲が忙しくても、自分の業務しかやらない |
 ひろやま
ひろやま時短勤務は「迷惑」ではなく、あなたの工夫と関わり方によっては、「信頼を築く」ことができますよ
看護師の時短勤務が迷惑だと思われる理由
- 業務の不公平感
- 業務量の偏りによる負担増加
- 突発的な欠勤・早退が多い
- 制度の理解がない・ジェネレーションギャップ
- 引き継ぎ・コミュニケーションが難しい
業務の不公平感
時短勤務者は、次のようなを業務を制限していることがほとんどです。
- 夜勤
- 遅番や早番
- 委員会
- 時間外の研修会や院外研修会
一方、フルタイム勤務者は当たり前のように、時短勤務者が制限している業務をこなしています。
そのため、「負担が一部の人に集中する」ことに不公平を感じるのです。
たとえば、このような業務がフルタイム職員に偏ると、不公平と感じてしまいます。
- 夜勤や遅番・早番の回数が増える
- 委員会の定例会議、報告書作成、院内発表などを限られたメンバーが継続的に担当する
- 時間外の勉強会はフルタイム勤務者は基本参加
- 院外の研修会はフルタイム勤務者に優先して声がかかる



制度上は問題なくても、感情的に「損している」と感じることが多いからこそ、時短勤務者への理解が得られにくいのね
業務量の偏りによる負担増加
時短勤務者が退勤したあとには、このような仕事を別のスタッフが引き継ぎます。
- 引き継いだ患者に対応した記録
- 引き継いだ患者の吸引や夕方に投与する点滴
- 引き継いだ患者のナースコールの対応
この仕事に加えて、突発的なケアや想定外の仕事が重なると、フルタイム職員が残業をするハメになってしまい、「なんで私ばかり忙しいんだろう」とストレスになります。
たとえば、他の職員の業務が増えてしまうと、このようなストレスを感じてしまいます。
- 予定より遅くまで働くことで、睡眠や休息の時間が削られ、ストレスとなる
- 家事や育児の時間が減り、ストレスを感じる
- 繰り返しの残業で体力が追いつかなくなり、ストレスになる



「しょうがない」と分かってはいても、実際に負担が増加するストレスは、フルタイム勤務者の不満となるのです
突発的な欠勤・早退が多い
予定外のシフト調整や、フルタイムの職員がその穴を埋めることになり、負担が増すため不満となリます。
たとえばフルタイム職員は、このようなシフト調整や勤務・業務の穴埋めに負担を感じています。
- 受け持ち患者の組み直しが必要になり、情報収集を最初からやり直すことになる
- 途中退勤したあとの業務をすべて引く継ぐため、丸ごと渡された患者のケア・記録・申し送りを代わりに全部やることになる
- 突発的な欠勤で急なシフト変更があり、休みだったのに急遽出勤になる
- シフト調整で連勤になったり、有給がとれなくなる
「またカバーしなくちゃいけないのか」ということが繰り返されると、不公平感やストレスが蓄積します。



自分が犠牲になっているように思ってしまうのね
制度の理解がない・ジェネレーションギャップ
制度の理解がない
「短時間勤務制度」は法律上、次のようなことが認められています。
- 3歳未満の子どもを育てる労働者は、希望すれば短時間勤務ができる
- 1日の所定労働時間を原則6時間(例:9:00~16:00)に短縮可能
- 介護の場合も条件を満たせば短時間勤務が認められる
- 夜勤や遅番を免除してもらえるケースが多い
- 勤務時間は病院によって、6時間勤務や7時間勤務などバリエーションがある
- 期間は子どもが3歳になるまでが法律上の最低基準だが、病院によっては小学校入学前まで延長可能な場合もある
子育てや介護と仕事の両立をしながら、職場を辞めずにキャリアを継続できる制度です。
制度の理解が浅いと「時短勤務=特別扱い」と感じるため「一部の人が楽をしている」と誤解されがちです。
このような時短勤務の働き方は、制度の理解がないと、特別扱いのように感じてしまいます。
- 残業なしで定時であがれることに対して、「ズルい」と感じる
- 夜勤免除や委員会の参加の制限に、「子供がいるから優遇されている」と思う



「時短勤務は権利」という認識がなく、働き方や業務の差を不公平と感じてしまいます
ジェネレーションギャップ
経験年数の高い世代と若い世代には、このような価値観のズレがあります。
| 経験年数の高い世代 | 若い世代 |
|---|---|
| 「家庭より仕事優先」 | 「家庭や子どもも大事」 |
| 育児を理由に業務を制限されること自体に抵抗を感じる | 制度を正当に使うことを当然だと捉えている |
「私が子育てしていたときは、誰にも迷惑をかけずにやっていた」と価値観のズレによりつい比較してしまい、不満が時短勤務者に向きがちです。
たとえば、経験年数の高い世代は、このように比較してしまいがちです。
- 「昔は誰も時短なんて使わずに、子育てしながら夜勤もしてたのに」と夜勤の免除を甘えと捉える
- 「私の時代は、子どもがいても普通に残業してたのに」と自分の経験を基準にしてしまう



「知ってはいるけど納得していない」ことが、時短勤務者への不満や不公平につながっているのね
引き継ぎ・コミュニケーションが難しい
引継ぎが難しい
申し送りの時間にいないため情報が正確に伝わらず、「業務が中途半端」「情報が共有されない」と誤解されやすくなります。
業務の負担や不安が残るため「迷惑」と思われてしまうのです。
時短勤務者からフルタイム勤務者への引継ぎは、このように正確に伝わらないことがあります。
- 急変や処置の詳細が伝わらない
- 患者家族からの、病状の説明希望などの重要な連絡が共有されない
- 時短勤務者の勤務時間内に医師から指示変更が出ても、他のスタッフ経由で聞くので詳しいことがわからない



引き継ぎ不十分だとインシデント要因にもなるため、フルタイム職員のストレスも増加してしまいます
コミュニケーションが難しい
勤務時間がズレることでコミュニケーションが取りづらく、信頼関係が築きにくくなります。
このように、コミュニケーションの機会が少ないと、フルタイム職員との信頼関係を築くのが難しくなります。
- 勤務の合間の自然な会話が減るため、相手の人柄や考え方を知る機会が少なくなる
- 休憩の時間が短くなったりズレることで、雑談などのコミュニケーションが減り距離感ができやすい
- 夕方以降の急変等に立ち会う機会が少なく、「一緒に大変な場面を乗り越える」という信頼形成のチャンスが減る



単に「時間が短い」だけではなく、交流の量が不足することで信頼関係を築くのが難しくなってしまうのです
看護師の時短勤務が迷惑だと思われないための3つの行動
- 日頃のコミュニケーションと感謝を大切にする
- 丁寧な引き継ぎと協力的な姿勢
- 業務は時間内に全力で取り組む
日頃のコミュニケーションと感謝を大切にする
感謝の気持ちを素直に表すことで、人間関係が良好になります。
そうすることで、お互いの人柄や事情を理解でき、不満が起きにくくなります。
このようなコミュニケーションは、人間関係が良好になり「協力しよう」という雰囲気が生まれやすくなります。
- 出勤時や退勤時の挨拶を欠かさない
- 同僚が業務を手伝ってくれたときにすぐに感謝を伝える
- 「この前の申し送り、わかりやすかったです」のように、同僚の仕事を認める言葉をかける
- 早く帰るときは、「お先に失礼します。 残りお願いします。」と一言添える
- 忙しいときに一言ねぎらいをかける



信頼と協力の土台作りには、素直な感謝とちょっとした気遣いの言葉が大切です
丁寧な引継ぎと協力的な姿勢
時短勤務でも「手を抜いていない」「周囲を気遣っている」ということが伝わり、同じ時間を過ごしていなくても「一緒にチームで働いている」という信頼が生まれます。
それが「仕事を放り出さない人」「仲間として信頼できる人」という印象に繋がり、逆に「迷惑」という印象を打ち消してくれます。
たとえばこのようにすることで、フルタイム勤務者に「周囲への気遣い」が伝わり、信頼関係が築きやすくなります。
- 「○○さん、今日はいつもより食事量が少なめです。夕方もう一度確認お願いします」などの口頭の送りとともにメモも一緒に残す
- 自分の業務が終わったあと「あと15分くらい余裕があるので、何かお手伝いできますか?」と申し出る
- 勤務終了時、「今日もありがとうございました。○○さんの件、お願いします」と感謝を伝えて退勤する



メモなどの気づかいや手伝いの申し出などの協力的な姿勢は、相手に好印象を与え、周囲も「迷惑」と思いにくくなりますよ
業務は時間内に全力で取り組む
時間内に全力で働く姿勢は、努力や責任感として伝わり、時短勤務でも「迷惑」ではなく「信頼できる仲間」と認識されます。
たとえば、日頃からこのように業務に取り組むことで、他の職員にも「努力している」「責任感がある」ことが伝わります。
- 申し送りや記録を他の誰よりも早く・正確に終えるように意識し、常に時間内に業務を完結
- 急変対応中のスタッフに「今できることありますか?」と声をかけ、限られた時間でも全力でサポート
- 自分の受け持ち患者の処置や検温、記録をすべて時間内に完了し、退勤前に周囲に状況を共有する



このような行動の積み重ねは「時短=迷惑」ではなく「信頼できる仲間」という評価につながっています
看護師の時短勤務が迷惑だと思われないために気をつけること4つ
- 自分優先になりすぎない
- 業務中の時間管理を徹底する
- 制度を当たり前と思わない
- 職場での発言に配慮する
自分優先になりすぎない
自分優先な行動には、次のようなものがあります。
- ナースコールが鳴っている中、定時になったからと無言で帰る
- 重症患者の急変対応で他スタッフがバタバタしている中、通常業務だけをして時間通りに退勤
- 「忙しいのはわかってるけど、私は時間なので」と言って、処置を途中で他人に任せて帰る
このような行動をしていると、同僚や上司に「フォローしてもらって当然と思っているの?」と受け取られ、「気遣いが足りない」といった不満を生みやすくなってしまいます。



私も、急変対応で忙しいときにいつの間にか時短勤務者が帰っていて、わかってはいてもさすがにイラっとした経験があるわ
不満を持たれないためにも、このようなことを意識・実践しましょう。
- チーム全体の状況を把握する習慣を持つ
- シフトや休暇希望は周囲の事情も考慮する
- 感謝とねぎらいを日常的に言葉にする
- 「やってもらう側」から「助け合う側」へ意識を切り替える
「早く帰りたいから」と自分のことばかり考えて動くのは禁物。
周囲の状況をみて協力できることは協力し、「お互い様」の気持ちでチームの一員として働く姿勢が大切です。
業務中の時間管理を徹底する
「限られた時間の中で責任を持って働いている」という姿勢が周囲に伝わり、仕事を任せられる信頼感が生まれるため、迷惑だとは思われにくくなります。
たとえば、業務中は次のように時間管理をしてみましょう。
- 朝のうちに優先度の高い業務から着手する
- 時間配分を意識し、こまめに進捗をチェックする
- 自分の業務時間内で終わらないことが予測される場合、早めに相談・共有する
時間の使い方や仕事への姿勢が問われるため、時短勤務であっても「全力で取り組んでいる」という印象が大切です。



「時短だから終わらなくてもしかたない」という気持ちは捨てましょう
制度を当たり前だと思わない
短時間勤務を「当たり前」だと思うような行動には、次のようなものがあります。
- 自分が退勤後の業務を他のスタッフが引き継いでも、感謝の言葉がない
- 自分の都合だけで勤務希望を出し、人で不足であっても柔軟に対応しない
- 時短勤務が「権利」であっても、それによって誰かが余分に負担している現実を意識せず、時間通りに帰れないことを主張する
短時間勤務は、周囲の協力や理解があってこそ成り立つ制度です。
現場では、短時間勤務を利用することで、他のスタッフが業務やシフトをカバーしているのが実情です。



同僚や上司の協力を「制度だから当たり前」だと思ってしまうと、不満がつのり、フォローしてもらえない状況になってしまいかねません
他のスタッフから協力や理解を得られるように、このように意識してみましょう。
- サポートを受けたら、自分も返す
- 日常的に感謝を伝える
- チームの負担状況を自分のこととして考える
- 時短勤務の理由を説明し、理解してもらえるように努力する
「制度を使えるのは周囲の協力があるからだ」という意識を言葉や行動で表すことで、同僚や上司も「私も大変だけど、できるだけ協力しよう」と前向きに思えるようになるのです。
職場での発言に配慮する
配慮がないと思われてしまう発言には、次のようなものがあります。
- 「時短だから仕方ないですよね。」
- 「時間だからもう帰ります。」
- 「夜勤は絶対できません。」
職場でのこのような発言は、「自分優先」「感謝がない」と受け取られ、不満を強め信頼関係が崩れてしましいます。
同僚や上司との関係性を悪化させないためにも、このように意識してみましょう。
- 感謝を先に伝える習慣をつける
- 同僚や上司の負担を想像して言葉を選ぶ
- 自分からもねぎらいの言葉をかける
- 「お願いします。 助かります。」のようにポジティブな言葉で締める
- 依頼や報告に「申し訳ないけど」などの柔らかい表現を添える
これらを意識することで、協力しやすい関係性を築きやすくなります。


現役看護師ひろやま
感染管理認定看護師
「ごめんね」より「ありがとう」の方が、関係がよくなる
病棟師長をしていたとき、時短勤務のスタッフが「迷惑をかけてすみません」「また早退してすみません」と何度も口にする姿をみてきました。
もちろん、謝る気持ちは大切です。でも私は「ごめんなさい」より「ありがとう」を伝える方が、職場の空気をあたたかくしてくれると感じてきました。
「ありがとう」には「あなたのおかげで働けています」という信頼と感謝が込められています。
職場の人間関係は、日々の小さな気づかいや声かけで、少しずつ築かれていくもの。
もしあなたが時短勤務で気まずさを感じているなら、どうか「ありがとう」の一言を大切にしてみてくださいね。
看護師の時短勤務が迷惑をかけていると思ったときにとる行動2つ
- 信頼できる先輩や上司に相談する
- 家族と緊急時の対応を決めておく
信頼できる先輩や上司に相談する
不安を一人で抱え込まずに、客観的な視点で具体的な改善策を得られます。
思い込みや自己否定を防ぐことができ、具体的な改善方法がわかることで信頼関係が築けるようになります。
たとえば、このような「思い込み」や「自己否定」が、相談することで「そうじゃなかったんだ!」と気が付くきっかけになります。
| あなたの思い込み・自己否定 | 上司や先輩の意見 |
|---|---|
| 自分ばかりがみんなに負担をかけている | 業務調整がされているため、実際は他のスタッフも協力体制に慣れているのでそこまで負荷はかかっていない |
| 私は戦力になっていない | 限られた時間でも、検査や処置などの多い日勤帯の時間にいてくれるので、とてもありがたい |
相談することで自分の思い込みを正したり、前向きな行動に切り替えるきっかけが得られます。



相談することは時短勤務でも安心して働き続けるための大事な一歩です
家族と緊急時の対応を決めておく
突発的な早退や欠勤を最小限に抑え、周囲への負担を減らすことができます。
たとえば、このように家族で対応を決めておきましょう。
| 具体例 | 家族との取り決め内容 | 得られる効果 |
|---|---|---|
| 子どもが発熱したとき | 〇曜日と〇曜日はパートナー、あるいは週〇回はパートナーが病院に連れていく | 曜日や週〇回と決められている日は、早退を気にせず勤務できる |
| 保育園からの急な呼び出し | 祖父母またはシッターに代行依頼する準備をしておく | 代わりの対応手段があり、職場への影響を最小限に |
| 朝、子どもの体調が微妙なとき | 「この症状なら今日は出勤、こうなったら休む」と基準を家族で共有 | 判断に迷わず、職場への連絡や調整がスムーズになる |



家族と事前に話し合い、対応策を決めておくことで、職場の信頼を得ることが可能になります
看護師の時短勤務が迷惑だと言われた・思われたときの対処方法2つ
- 職場の相談窓口や労働組合に相談する
- 部署異動や転職を検討する
職場の相談窓口や労働組合に相談する
同僚や上司から露骨に「時短勤務なんて迷惑」と言われた場合はハラスメント行為に当たります。
直接言われていなくても、必要以上に委縮する必要はありません。
一人で抱えこまずに相談することで、自分の働き方を守り、安心して働ける職場づくりにつながります。
たとえば、職場でこのようなことがあったときは、迷わず相談してみましょう。
- 「あなたが早くか帰るから残業になる」と繰り返し言われ、精神的に辛い
- 「時短は特別扱い」「昔はそんな制度なかった」と言われ、制度を使いづらい雰囲気がある
- 「あの人だけ楽してる」といった陰口を他のスタッフから聞いて、仕事に行くのが辛い
- 時短勤務を理由に評価を下げられ、昇給や賞与にも影響していると感じる
相談することは「自分を守る手段」であると同時に、職場全体の意識や仕組みを変えるきっかけにもなります。
参考:厚生労働省:「職場のパワーハラスメント対策に係る自主点検票の解説」 /日本労働組合総連合会「労働相談」
部署異動や転職を検討する
制度を正しく理解・運用してくれる職場で働く方が、ストレスを感じず働けます。
どうしても状況が改善しないなら、自分を責めたりやる気を失わないためにも、部署異動や転職を検討しましょう。
このように、一部の人に負担がかからないように業務調整がされていると、時短勤務でも安心して働けます。
- 病棟での業務配分を工夫し、時短勤務者とフルタイム職員の負担が均等になる仕組みがある
- 時短勤務者とフルタイム勤務者をペアリングする構成をとり、お互いに補完し合える体制をとっている
- 周囲の協力を当然と思わずに、感謝や声かけが自然に行われている
- 相談しやすい環境が整っている



「時短勤務は迷惑だ」と繰り返し言われるような職場では、自分の努力だけで状況を変えるのは難しいですよね
部署異動や転職を検討することは、長く安心して働くための前向きな選択肢になります。
看護師の時短勤務で迷惑をかけずに時間で帰る3つの方法
- 日頃からチームと密に連携する
- 業務に優先順位をつけて効率化
- 早く帰る日は意思表示をはっきりする
日頃からチームと密に連携する
普段から積極的にコミュニケーションをとることで、助け合える関係を築くことができます。
関係性が築けていると、協力しようという気持ちになるため、定時退勤が受け入れやすくなります。
日頃からこのようなことを意識すると、自然にフォローし合える関係が築けます。
- 業務状況や予定をこまめに共有する
- 困ったときは早めに相談・依頼する
- 小さな感謝もその場で伝える



日頃の連携と気遣いが、信頼と協力の関係を築く土台となります
業務に優先順位をつけて効率化
業務の段取りと所要時間を意識して働くことで、無駄なく仕事が進み残業を減らすことができます。
次のようなことを意識して、実践してみましょう。
- 患者の清潔ケアや処置が多い日は、朝のうちに優先順位を確認し、「時間内に終えられる処置」と「他スタッフに相談が必要な処置」を分けて計画的に動く。
- 申し送りの準備・記録・報告を後回しにせず、観察やケアの合間にこまめに入力・記載しておく。
- 「今日やるべきこと」「今日中でなくても支障のないこと」を朝のカンファレンス時に整理し、必要に応じてリーダーへ相談する。



「今やるべきこと」を見極めて効率よく動くことで、周囲にも配慮しながら、自分の業務もきちんと終える働き方ができます
早く帰る日は意思表示をはっきりする
どうしても定時で帰らなければならない日は、朝のうちに上司や周囲に伝えておくことで、周りも心づもりができます。
今日はどうしても定時に帰りたいと思ったらこのように伝えてみましょう。
- 「今日は◯時までなので、この処置と記録を午前中に終わらせます」と朝の申し送り時に伝える。
- 「子どもの健診があるので、時間ぴったりに上がらせてもらいます」とリーダーに朝のうちに相談する。
「今日は◯時までに帰ります」と朝のうちに伝えるだけで、周囲は対応の準備ができ、信頼と協力関係が築けます。



場合によっては、働く部署や勤務形態を見直すことも視野に入れ、自分が時間通りに帰れる働き方を模索するのも1つですよ
よくある質問
育休明けの時短勤務は迷惑ですよね?辞めた方がいいですか?
育休明けに時短勤務を利用することは迷惑ではありません。
迷惑かけるからという理由で辞める必要もありません。
育休明け看護師の時短勤務は「権利」であり、働き方次第でチームに必要とされる存在にだってなれます。
職場も貴重な人材が辞めずに済んでいるという側面もあります。
復帰後はこのようなことを意識してみましょう。
- 復帰後すぐに「時間内でできることは責任を持ってやります」と宣言し、看護記録や清潔ケアなどを効率的にこなす。
- 育休明けで復帰したが、申し送り内容を簡潔にまとめ、午前中に優先度の高い処置や検温などを率先して実施。
- 時短で退勤する前に、物品補充や翌日の準備など“その場でなくても助かる仕事”を積極的にこなす。
まずは続けられる道を探ってみましょう。
本文で紹介した対策を試しても職場の理解が得られない場合は、育児と両立しやすい職場への転職も選択肢の1つです。
病棟で時短勤務をしています。子どもの体調不良での早退や欠勤で肩身の狭い思いをしています。どうたらいいですか?
事前準備と周囲への共有が有効です。
急な早退や欠勤を完全に防ぐことはできなくても、「事前に備えて共有しておくこと」で信頼関係を保ち、周囲の負担を最小限にできます。
次のようなことを実践してみてください。
- 朝の申し送り時に「子どもが微熱で、呼び出されるかもしれません」とリーダーに伝えておく。
- 前日のうちに「明日、子どもの具合が良くなければ休む可能性があります」とチームに共有する。
- 「もし途中で呼び出しがあっても記録はここまで終わらせておきます」と業務の優先順位を伝えてから勤務する。
- パートナーや家族と「誰が迎えに行くか」「看病はどう分担するか」を話し合っておく。
日頃から業務の情報共有や引継ぎをしっかりおこない、「急に抜けても大丈夫な体制」を整えておきましょう。
時短勤務で働いていますが、なかなか時間通りに帰れません。どうしたらいいですか?
業務の優先順位を見直し、時間管理を改善しましょう。
それでも難しいなら、上司に相談して業務内容や配置を調整してもらいましょう。
業務の優先順位を見直し時間管理を改善することで、限られた時間でも成果を出し、無理なく定時退勤できるようになります。
たとえば、このようなことを実践してみましょう。
- 「観察、処置の合間にこまめに記録する」ようにし、記録業務を後回しにしない。
- 「午前中に終えるべき業務」と「午後でもよい業務」をリスト化して勤務前にチーム内で共有する。
- 物品補充や記録の整理など、あとでもできるが忘れやすい業務を退勤前にまとめてやろうとしない。
優先順位とタイミングを見直すだけで、仕事の流れが整い、時短勤務でも「やることはきちんと終える人」として周囲からの信頼も得られます。
まとめ:看護師の時短勤務が迷惑と思われないために必要なのはお互いの気遣い
育児中の看護師にとって時短勤務制度は必要不可欠ですが、職場の協力なしには成り立ちません。
そして、周囲のサポートがあってこその制度である以上、利用する側の配慮も欠かせません。
時短勤務だからと必要以上に遠慮せず、「困ったときはお互い様」という気持ちで日々の業務に取り組むことが大切です。
そうすれば、きっと周囲も理解を示してくれるでしょう。
育休明けのママ看護師もベテラン看護師も、まずは明日から「ありがとう」を伝えることから始めてみませんか。
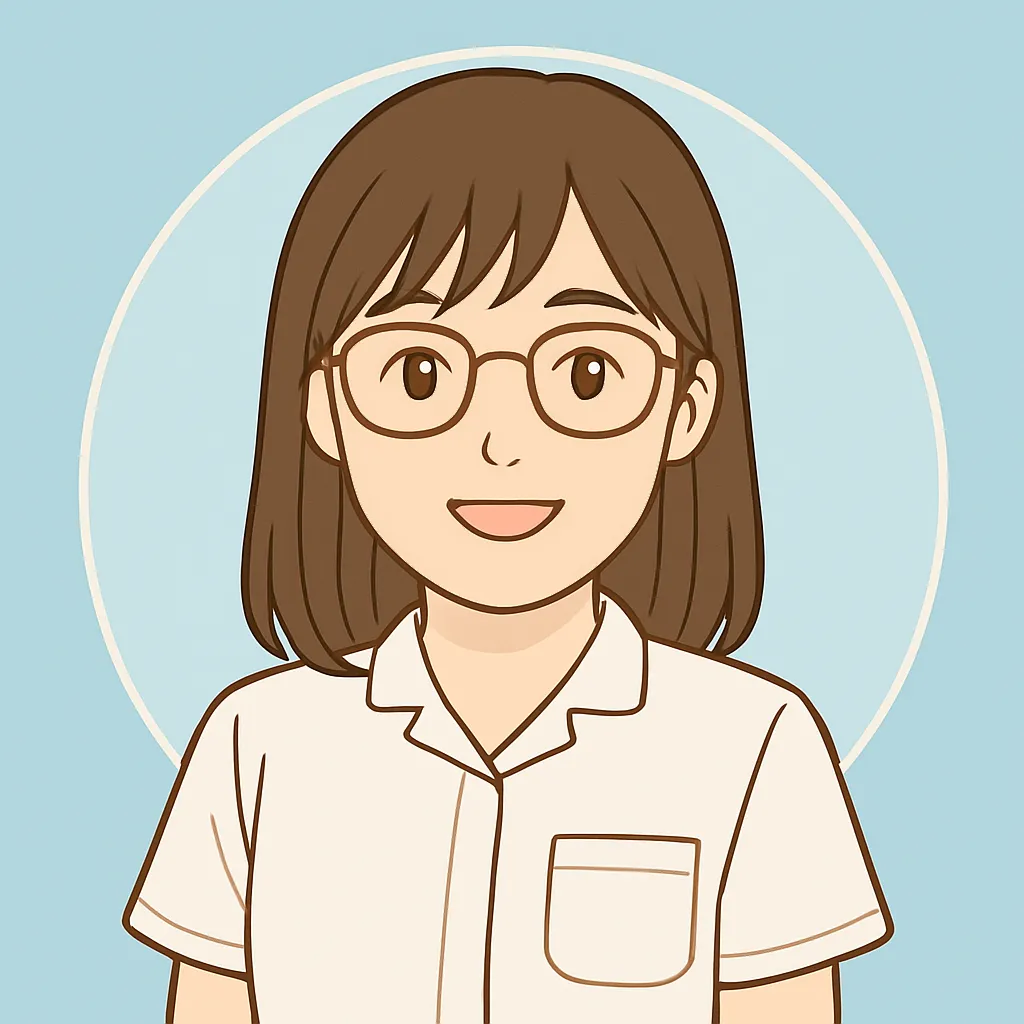
コメント